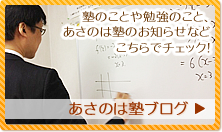2023,11,07, Tuesday
「どうしても雪だよ、おっかさん谷のこっち側だけ白くなっているんだもの。どうしても雪だよ。おっかさん」すると母親の熊はまだしげしげ見つめていたがやっと言った。「雪でないよ、あすこへだけ降るはずがないんだもの」子熊はまた言った。「だから溶けないで残ったのでしょう」「いいえ、おっかさんはあざみの芽を見に昨日あすこを通ったばかりです」
月の光が青じろく山の斜面を滑っていた。そこがちょうど銀の鎧のように光っているのだった。しばらくたって子熊が言った。「雪でなけぁ霜だねえ。きっとそうだ」
◆◇◆◇◆
「おかあさまはわかったよ、あれねえ、ひきざくらの花」「なぁんだ、ひきざくらの花だい。僕知ってるよ」「いいえ、お前まだ見たことありません」「知ってるよ、僕この前とって来たもの」
「いいえ、あれひきざくらでありません、お前とって来たのきささげの花でしょう」「そうだろうか」子熊はとぼけたように答えました。
小十郎はなぜかもう胸がいっぱいになって、もう一ぺん向うの谷の白い雪のような花と、余念なく月光をあびて立っている母子の熊をちらっと見て、それから音をたてないようにこっそりこっそり戻りはじめた。
(宮沢賢治『なめとこ山の熊』から)
◆◇◆◇◆
ふと、勇の視界に、黒い人影が映った。その影は、雨の中をゆっくりと進んできていた。水溜まりを大股にまたいだ。傘が動いて、耳の下まで垂れた長い髪が勇の眼に入った。
おとうちゃーん。
勇は叫んでいた。父親は勇の前までくると、腰をかがめて、小さな水色の長靴を置いた。新品だった。いままで穿いていたものは、底に穴が開いてしまっていた。
むかえにきてくれたの?
父親は何も言わずに、勇に長靴を履かせた。ぴったりと勇の足は長靴に納まった。
◆◇◆◇◆
あたらしくかったんだね。
ああ。
ほとんど聞きとれないほど、低い声で父親は答えた。幼稚園に、父親が来たのは初めてのことだった。勇は、父親のさす傘の下で歩きながら、温かい風が胸の中をそよいでいる気がしてきて仕方がなかった。
おとうちゃんがきてくれたんだ、何度もそう思って、尖った頬骨を前に向けて、無言で歩き続ける父親を見上げた。跳びはねると、父親におこられることが分かっていたので、足をしっかりと緊張させて歩いた。
(高橋三千綱『九月の空』から)
◆◇◆◇◆
少年は毎朝 『白百合』の生徒たちが乗る江ノ島行きの電車に 合わせて家を出るのである。彼女はその十分前に玄関を出てくる。
その朝、彼女がちょうど門から出てきたところへ少年が行った。少年の心はおどった。 まだ二十メートルもはなれていた。その二十メートルを彼はうつむいて歩いた。
彼女は門のそばの石垣にもたれるようにしていた。頭をかしげて、年上らしい落ちついた 目をして。
「おはよう。」彼女のほうから大きな声でいった。
少年はもっと近づいてから、それも小さな声でしかいえなかった。彼は何かいわれてもただおどおどするだけだった。 そしてひどく急ぎ足になった。
◆◇◆◇◆
彼女は小走りしながら腕時計を見た。「何分の電車に乗るの? おくれそう?」
「さあ、どうかな。」彼は逃げるようにして、わき目もふらずにとっとと歩いた。「じゃあ走れば。 いっしょに走ってあげる。」
そこで彼は走り出した。これはおかしなことになったと思いながら。彼女も走ったけれど、たちまち少年にひきはなされた。
彼はかまわず走りつづけた。走りながらやっぱりどうしても彼女を好きなのがわかった。 好きだ。彼はうしろも見ずに走った。
彼女は途中でのびてしまっていた。少年がふりかえると、手で小さなバイバイをして先に行けといった。「おくれるといけないわ。」
で、彼はまた走らなければならなかった。
(阿部昭『幼年詩篇』から)
◆◇◆◇◆
一人の生徒が病気で亡くなりました。道半ばの夭逝でした。ご冥福をお祈り致します。
「いいえ、あれひきざくらでありません、お前とって来たのきささげの花でしょう」「そうだろうか」子熊はとぼけたように答えました。
小十郎はなぜかもう胸がいっぱいになって、もう一ぺん向うの谷の白い雪のような花と、余念なく月光をあびて立っている母子の熊をちらっと見て、それから音をたてないようにこっそりこっそり戻りはじめた。
(宮沢賢治『なめとこ山の熊』から)
◆◇◆◇◆
ふと、勇の視界に、黒い人影が映った。その影は、雨の中をゆっくりと進んできていた。水溜まりを大股にまたいだ。傘が動いて、耳の下まで垂れた長い髪が勇の眼に入った。
おとうちゃーん。
勇は叫んでいた。父親は勇の前までくると、腰をかがめて、小さな水色の長靴を置いた。新品だった。いままで穿いていたものは、底に穴が開いてしまっていた。
むかえにきてくれたの?
父親は何も言わずに、勇に長靴を履かせた。ぴったりと勇の足は長靴に納まった。
◆◇◆◇◆
あたらしくかったんだね。
ああ。
ほとんど聞きとれないほど、低い声で父親は答えた。幼稚園に、父親が来たのは初めてのことだった。勇は、父親のさす傘の下で歩きながら、温かい風が胸の中をそよいでいる気がしてきて仕方がなかった。
おとうちゃんがきてくれたんだ、何度もそう思って、尖った頬骨を前に向けて、無言で歩き続ける父親を見上げた。跳びはねると、父親におこられることが分かっていたので、足をしっかりと緊張させて歩いた。
(高橋三千綱『九月の空』から)
◆◇◆◇◆
少年は毎朝 『白百合』の生徒たちが乗る江ノ島行きの電車に 合わせて家を出るのである。彼女はその十分前に玄関を出てくる。
その朝、彼女がちょうど門から出てきたところへ少年が行った。少年の心はおどった。 まだ二十メートルもはなれていた。その二十メートルを彼はうつむいて歩いた。
彼女は門のそばの石垣にもたれるようにしていた。頭をかしげて、年上らしい落ちついた 目をして。
「おはよう。」彼女のほうから大きな声でいった。
少年はもっと近づいてから、それも小さな声でしかいえなかった。彼は何かいわれてもただおどおどするだけだった。 そしてひどく急ぎ足になった。
◆◇◆◇◆
彼女は小走りしながら腕時計を見た。「何分の電車に乗るの? おくれそう?」
「さあ、どうかな。」彼は逃げるようにして、わき目もふらずにとっとと歩いた。「じゃあ走れば。 いっしょに走ってあげる。」
そこで彼は走り出した。これはおかしなことになったと思いながら。彼女も走ったけれど、たちまち少年にひきはなされた。
彼はかまわず走りつづけた。走りながらやっぱりどうしても彼女を好きなのがわかった。 好きだ。彼はうしろも見ずに走った。
彼女は途中でのびてしまっていた。少年がふりかえると、手で小さなバイバイをして先に行けといった。「おくれるといけないわ。」
で、彼はまた走らなければならなかった。
(阿部昭『幼年詩篇』から)
◆◇◆◇◆
一人の生徒が病気で亡くなりました。道半ばの夭逝でした。ご冥福をお祈り致します。
あさのは塾便り::勉強・子育てなど | 12:53 AM | comments (x) | trackback (x)